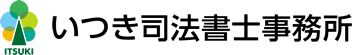公正証書遺言 証人
- 遺言書の種類と効力
普通の方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。 〇自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です。自筆証書遺言が法的効力をもつためには、①「全文」の自書、②「日付」の自書、③「氏名」の自書、④押印の4つを満たさなければなりません(民法968条1項)。ただし、遺...
- 公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことを指します。公証人が関与することで、遺言書作成における不備で無効になることや紛失を防ぐことなど多くのメリットがあります。しかし、自身で作成する遺言書と異なる点として、適切な手続きを踏まなければならないことが挙げられます。ここでは、公正証書遺言の作成に...
- 公正証書遺言の効力|無効になってしまうのはどんなケース?
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。中でも公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、一番確実性や信頼度が高く、効力の高い遺言書といわれています。その効力が高い公正証書遺言であっても、無効になってしまうケースがあるのです。今回は、公正証書遺言が無効になってしまうケースに...
- 公正証書遺言について~効力や特徴、自筆証書遺言との違い~
つではなく、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などの種類を遺言者は選択することができます。 記載できる遺言に違いはありませんが、遺言書の有効性について争いが起こる可能性なども考慮して選ぶことが大事です。そこで当記事では代表的な上記2種の遺言書につき比較検討ができるよう、特に公正証書遺言へ焦点を当てて解説をしていき...
- 遺言書の保管方法を解説|自宅・貸金庫・公証役場・法務局での保管について
公正証書遺言は公証役場で保管遺言書にも種類があります。 「公正証書遺言」と呼ばれるタイプは、遺言書を、公証を受けた公正証書として作成したものです。公証役場で手続を行い、公証人に文書を作成してもらうことで完成します(遺言内容は本人が考える)。 そして公正証書遺言の場合、原本が公証役場で保管することが決まっています。...
- 遺贈手続きの流れと遺言内容の検討をするときのポイントについて
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言、その他死亡の危機に瀕したときに作成できる遺言書、隔離された状況下で作成できる遺言書などがあります。 それぞれ作成方法については民法でルールが定められており、所定の方式に従って作成ができていなければ遺言書が無効になってしまいます。 例えば、よく利用される①と...
- 遺言書作成の流れと必要書類、作成費用について
そこで当記事では代表的な遺言書(自筆証書遺言と公正証書遺言)について、具体的な作成の方法、作成の流れ、必要書類と作成費用について解説していきます。遺言書作成の流れ遺言書の清書を始める前に、遺言内容を考える必要があります。そして財産の受け取り手や遺産分割の方法などを指定する場合、前もって法定相続人や財産の内容等を把...
- 遺言書の種類| 作成方法や費用、メリット・デメリットを種類別に解説
特に代表的な遺言書である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」については、近年の法改正の影響や費用など、詳細も併せて紹介していきます。遺言書の種類遺言書の種類は、大別すると「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つに分けられます。2つの方式について説明していきます。普通方式遺言普通方式遺言は、下表にある3つの遺言のことを...
- 認知症に備える相続・遺言対策について解説
公正証書遺言の活用早めに遺言書を作成しておくことで、遺言能力の有無を争点とするトラブルを防ぐことができます。また、「公正証書遺言」として作成しておくとより安全性を高められます。 公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言書のことで、遺言者自身が作成する自筆証書遺言とは異なり、作成手続きに直接的に公証人が関与します。
- 公正証書遺言の証人になれるのはどんな人?手配の方法は?
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成して残す遺言のことをいいます。公正証書遺言には証人が2人、必要となり証人になれない人が法律によって定められています。今回は、公正証書遺言の証人になれるのはどんな人で、どのように手配したいいかを紹介していきたいと思います。公正証書遺言の証人になれない人の要件公正証書遺言の証人...
- 会社設立時に司法書士に依頼できること
定款の作成が済んだら、公証人役場に定款の認証申請をします。そして資本金振込みの手続きが終わったら、登記申請です。申請が受理される目安としては、だいたい1~2週間後です。設立登記が完了すると、「登記簿謄本」や「会社の印鑑証明書」を取得することができます。 会社設立についてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご相談...
- 相続問題で司法書士に依頼できること
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言を作成する場合、遺言者1人で作成可能である反面、形式面の不備により遺言が無効となってしまうおそれがあります。そこで、自筆証書遺言の作成の際に内容面・形式面の両方を司法書士に相談することによって、相続トラブルを未然に回避することがで...
- 合同会社と株式会社の違いについて
その内容は、定款認証の際に公証人に支払う費用や登録免許税、定款用収入印紙代等、合計で20万円程度かかります。その一方、合同会社は株式会社の設立に必要だった定款の認証が不要であるため、その分設立費用を安く抑えることができ、最低6万円からの設立が可能です。 会社設立などについてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご...
- 会社設立に必要な定款とは?記載事項や作成の流れ
定款認証とは、作成した定款を公証役場で公証人に認証してもらうことを指します。ここで、定款が適切に作成されているか判断され、認めてもらえれば、公的に定款が適切に作成されたことが証明されたことになります。 以上が定款についての説明になります。会社設立には、多くの手続きが必要となり、その中でも定款作成は手間のかかる手続...
- 遺言書の検認手続き|手続きの流れや必要書類など
具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言であり、被相続人の死亡時に遺言書が見つかった際に検認手続きが必要になるのは、自筆証書遺言です。 自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです(但し財産目録についてはパソコンによる作成も可能です)。この自筆証書遺言が見つ...
- 相続の対象になる財産とは? 相続対象外の財産や注意が必要な財産など紹介
ほかにも、親権や従業員としての地位、生活保護受給権、年金受給権、身元保証人としての地位、離婚の請求権なども一身に専属する権利として、相続の対象外となります。 生命保険金前項で紹介したものは、亡くなった方、つまり「被相続人に固有の権利」です。 これに対して、「相続人に固有の権利」もあります。被相続人の死亡をきっかけ...
- 不動産の共有名義人のいずれかが死亡した場合の相続手続き
公正証書遺言秘密証書遺言 遺言書には注意点があり、遺言書保管制度を利用していなかった自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかったときには、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。相続人を確定する被相続人が亡くなった後に誰が相続人に該当するのか、被相続人の戸籍謄本を取得して調査を行い、相続人を確定します。遺産相続の対象...
- 相続人の調査| 集める戸籍の種類や取得方法、その他相続手続で調査が必要な事項
公証役場で作成する「公正証書遺言」については、原本が公証役場で保管されています。どこの公証役場で保管されているものであっても、最寄りの公証役場から調べることが可能です。遺産の内容と価額遺産は遺産分割の対象となりますので、把握できていないと協議を進められません。また、各財産について価額の評価も進めておきましょう。
- 任意後見を始めるには2段階の手続きが必要|契約や申し立ての流れ、費用を解説
公証人との打ち合わせを通じて必要書類や手続きの詳細を確認する本人と任意後見受任者が公証役場に出向いて任意後見契約を締結。公証人が契約内容を確認し、最終的な契約書(公正証書)を完成させる。任意後見契約に関する登記任意後見契約の公正証書を作成した後で、公証人が登記所に対し登記の嘱託をします。登記は必須ですが、契約当事...
- 遺言書作成前に知っておきたい遺言執行の基礎知識
※公正証書遺言、法務局で保管されていた自筆証書遺言では不要。遺言執行者が就任について承諾をする就任したことを相続人に知らせる相続財産を調査し、財産目録を作成する各種財産を記載内容に従って引き渡し、登録制度などに従うものは名義変更の手続を行う(不動産の所有権移転登記など)相続人への報告 各手続きにかかる期間は、遺言...
- 後見制度で将来に備える|後見人の種類とそれぞれの利用シーンとは
借金の保証人になる遺言書の作成 など補助人比較的軽度の判断能力の低下が見られる方を支援するため、「補助人」が選任されます。 例えば初期の認知症の方、知的障害・精神障害などにより日常生活はおおむね自立して行えるものの、高額な取引や不動産の売買など重要な法律行為を行う際には判断能力の面で不安が残るといったケースが該当...
- 成年後見制度の利用にかかる費用|申立手数料や後見人等への報酬額について
公証人に支払う手数料・・・11,000円証書の枚数が4枚を超えると1枚あたり250円加算。病床にて証書を作成するときは通常費用の50%を加算。登記手数料としての収入印紙代・・・2,600円登記嘱託の手数料・・・1,400円正本や謄本の作成手数料・・・1枚あたり250円出張作成を依頼する場合・・・1日につき2万円+...
- 法定後見制度利用の流れ|後見・保佐・補助の違いや任意後見との比較
認知症や知的障害・精神障害などが原因で法的に「判断能力が不十分」とされる場合、生活に必要なサービスを利用したり財産を適切に管理したりすることが本人には難しくなってしまいます。このような方を法的に支援する制度が成年後見制度で、この制度の1種である「法定後見制度」が割合多く利用されています。ここでも法定後見制度に焦点...
- 認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できるケース
家族信託の契約を締結する際には、公証人や司法書士などの専門家が面談を行い、判断能力の有無を判定していきます。判断能力の判定のために、どのような質問が問われるのでしょうか。公証人が行う具体的な質問内容は以下のようなものになります。 本人の氏名、住所、生年月日の確認信託に入れる財産について誰に財産を託したいかなど亡く...
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ