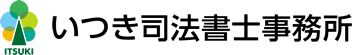成年後見制度を利用する前に確認すべき注意事項
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法的に保護し支援する仕組みとして有効な制度です。
しかし、いざ利用を検討する段階になって初めて気づく注意点や制約が存在するのも事実です。
当記事では、制度利用前に確認しておくべき重要な注意事項について紹介していますので、一度目を通していただければと思います。
申立て前に理解しておくべき本人に対する制限
成年後見制度の利用は、本人の権利を守るためのものでありながら、同時に一定の権利制限を伴います。
この制限は、本人とその家族の従来の生活様式に大きな変更を迫る可能性があることから、申立て前の慎重な検討が求められます。
たとえば、被後見人となった方は、日用品の購入といった日常的な買い物を除き、自身での契約締結が制限されることとなります。
また、これまで家族間で行ってきた財産管理の方法についても、一定の制約を受けることになるでしょう。
具体的には、子どもへの定期的な仕送りや、これまで行ってきた贈与などの継続が困難となる可能性があるほか、自宅の売却といった不動産取引に関しても家庭裁判所の許可なしには実施できないといった制限が生じることとなります。
申立て時に直面しやすい問題
成年後見制度の申立ては書類を揃えて提出するだけの手続きのように思えるかもしれません。しかし、診断書の取得や、法的な要件ではないものの親族間での合意形成が重要となるなど、申立てにあたって予期せぬ困難に直面することも少なくありません。
診断書取得における課題
医師の作成する診断書は、申立ての成否を左右する重要な資料です。
主治医がいない場合であれば、まずは地域の医療機関に相談しましょう。また、診断書の記載内容が成年後見制度利用の観点から不十分な場合もありますので、司法書士などの専門家に協力してもらいながら家庭裁判所が求める事項を具体的に記してもらう必要があるでしょう。
なお、診断書の提出だけで本人の判断能力の程度を明確に示せないときは、家庭裁判所から「鑑定」を命じられることがあります。
この場合、鑑定費用として10万円~20万円ほどの負担が発生してしまいますので、申立て前から本人の状態を医療機関で定期的に確認しておくことがスムーズな手続きのために重要といえるでしょう。
親族間での意見対立
後見人の選任をめぐって、しばしば親族間で意見の対立が生じます。このような事態を避けるため、申立て前の段階から、後見人候補者の選定方法や財産管理の方針について、十分な話し合いの機会を持つことが重要といえるでしょう。
特に、親族後見人を選任するか、あるいは司法書士などの専門職後見人を選任するかについては、本人の財産状況や親族間の関係性を踏まえた慎重な判断が求められます。後見人には継続的な財産管理と報告の義務が伴うため、これらの業務を適切に遂行できる人物を選定する必要があるのです。
希望する方が後見人になれるとは限らない
後見人の選任は、最終的に家庭裁判所の判断に委ねられます。
そのため、本人や親族が希望する人物が必ずしも後見人として選任されるとは限らないという点は、申立て前に十分理解しておく必要があります。
家庭裁判所は、本人の福祉を最優先に考え、財産管理能力や本人との利害関係の有無、さらには後見事務を継続的に遂行できる能力の有無など、さまざまな観点から後見人選任の判断を行います。
そこでたとえば、本人の預貯金が高額である場合や、不動産取引が予定されている場合などには、親族ではなく専門職後見人が選任されるケースも見られます。
後見人の責任は重たい
後見人となった方も成年後見制度の仕組みをよく理解し、自身が何をしないといけないのか、どのような責任を負うのかを意識しておく必要があります。
たとえば本人の生活・療養看護・財産管理に関する包括的な責任が課せられます。
※成年後見人、保佐人、保佐人のいずれに選任されるのかによっても責任の範囲は異なる。
基本的には、本人の財産状況を継続的に把握すること、定期的に収支報告書を家庭裁判所に提出すること、などが求められます。
この報告には領収書等の証拠書類の添付が必要となることもあり、不適切な財産管理や不正行為が発覚した場合には、後見人が解任されるだけでなく損害賠償責任を負う可能性もあるのです。
別の制度も検討しよう
成年後見制度がすべてのケースにおいてベストな選択であるとは限りません。
状況に応じてより最適な手法を模索する姿勢も重要であり、初めから成年後見制度の利用を決めつけず、代替制度の活用も視野に入れましょう。
たとえば、現時点では判断能力がある方の場合、「任意後見制度」の利用が適している可能性があります。
任意後見も成年後見制度の一種ですが、後見・保佐・補助などの判断能力が衰えて事後的に利用する法定後見とは異なる性質を持ちます。
将来の後見人を自分で選ぶことができますし、委任する事務の内容も細かく指定することが可能です。
また、比較的軽度の認知症の方であれば「日常生活自立支援事業(自立して生活できるよう、福祉サービス等の利用援助を行うもの)」の利用で十分な場合もあります。さらに、最近では「家族信託(家族など身近な方を受託者として財産の管理運用を委託する)」を活用するケースも増えており、信託の仕組みを利用すればより柔軟な財産管理が可能となります。
このように、支援を必要とする方の状況や希望に応じて、最適な制度を選択することが望ましいといえます。
そのためにも、成年後見制度の利用を検討する際には、専門家に相談のうえ、複数の選択肢の中から最適な方法を選ぶことをおすすめします。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ