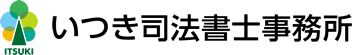認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できるケース
家族信託とは、特定の財産を信頼できる家族へ託すために使われる制度のことです。
家族が認知症になったあとも、家族の財産を管理できるようにしたいケースなど、家族信託が選択されることがあります。
今回は、認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できるケースについて紹介していきたいと思います。
初期や軽度の認知症の場合、家族信託を利用できるケースがある
基本的には、すでに認知症となり判断能力が失われている場合には、家族信託を利用することはできません。
認知症になってしまうと、契約内容自体が自分自身に利益があるのか不利益となるのか、判断ができなくなってしまうからです。
しかし、例外的に認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できるケースがあります。
初期や軽度の認知症の場合、認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できる可能性があります。
初期や軽度の認知症の場合、日常生活への支障はほとんどないものの、物忘れのような記憶障害がみられることがあります。
軽度の認知症では、認知症の一歩手前の段階で、判断能力が正常と認知症の間の状態とされるものです。
こういった場合、契約内容を問題なく理解していると認められれば、認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できる可能性があります。
判断能力について、どのように判定されるのか
家族信託の契約を締結する際には、公証人や司法書士などの専門家が面談を行い、判断能力の有無を判定していきます。
判断能力の判定のために、どのような質問が問われるのでしょうか。
公証人が行う具体的な質問内容は以下のようなものになります。
- 本人の氏名、住所、生年月日の確認
- 信託に入れる財産について
- 誰に財産を託したいかなど
- 亡くなった後、誰に相続させたいか
上記のような家族信託の契約内容についての質問を理解して回答できた場合、判断能力が有り、契約内容について十分に理解できる状態と判定されて、たとえ認知症の診断を受けたあとでも家族信託の契約を進めることができる可能性があります。
まとめ
今回は、認知症と診断されたあとでも家族信託を利用できるケースを紹介していきました。
認知症と診断されたあとでも家族信託を利用する場合には、症状が軽度であれば利用できる可能性があり、判断能力の有無が重要となります。
判断能力の有無の判断には専門的な知識が必要となりますので、家族信託の利用を検討している場合には、早めに司法書士に相談することを検討してみてください。
よく検索されるキーワード
司法書士紹介

代表司法書士 武田一樹
私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?
お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
-
- 所属団体
-
東京司法書士会(登録番号3502)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
-
- 経歴
-
平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
事務所概要
| 事務所名 | いつき司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
| 電話番号 | 0422-24-7924 |
| FAX番号 | 0422-24-7925 |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
周辺マップ